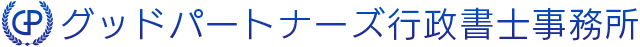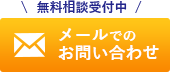コラム
column
遺産分割のやり直しは???
遺産分割のやり直しは、可能か???
遺産分割が完了した後でも、状況によっては「遺産分割のやり直し(再分割)」が可能な場合があります。以下に、やり直しが可能な主なケースとその方法について解説します。
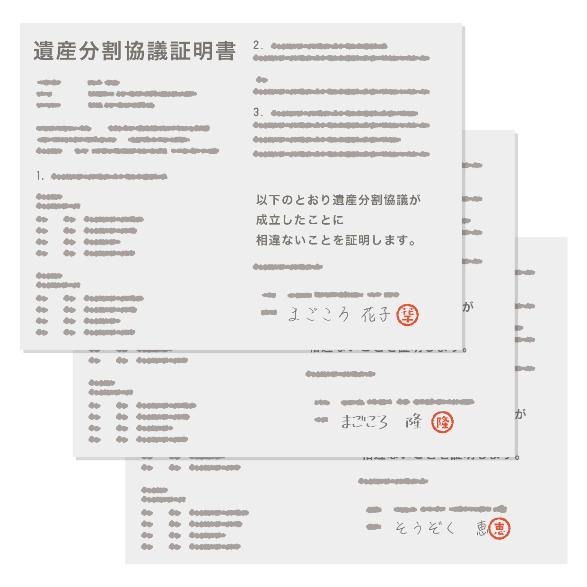
(1) 相続人全員の合意がある場合
すでに遺産分割が完了している場合でも、相続人全員が合意すれば、改めて遺産分割をやり直すことが可能です。この場合、新たに「遺産分割協議書」を作成し、名義変更や登記などの手続きを行います。
(2) 遺産分割協議の無効・取消し・解除
以下のような事情がある場合、すでに行われた遺産分割協議が「無効」または「取消し」となることがあります。
- 詐欺や強迫があった場合
- 一部の相続人が騙されたり、脅迫されたりして遺産分割協議を締結した場合は、その協議を取り消すことができます。(民法96条)
- 錯誤(勘違い)があった場合
- 例えば、遺産の内容について誤った認識のもとで協議が行われた場合(特定の財産が遺産に含まれていると誤認した等)、錯誤を理由に無効を主張することができます。(民法95条)
- 重大な事実の隠匿・不正行為
- 例えば、特定の相続人が他の相続人に財産の存在を知らせずに遺産分割を行った場合、不正行為を理由に協議を取り消すことが可能です。
- 相続人の一部が関与していなかった場合
- 相続人全員の参加が必要な遺産分割協議において、特定の相続人が参加していなかった場合は、その協議は無効となり、やり直しが必要になります。
(3) 未分割の財産が見つかった場合
遺産分割協議後に、新たに遺産が発見された場合、その財産については新たに遺産分割協議を行う必要があります。この場合、すでに行われた遺産分割の内容は変更せず、新たな財産のみを対象に協議することができます。
(4) 特別受益や寄与分の考慮漏れ
遺産分割後に、ある相続人が被相続人から生前に特別な援助(特別受益)を受けていたことが判明した場合や、特定の相続人が被相続人の介護などに貢献していた(寄与分)ことが適切に考慮されていなかった場合、家庭裁判所で遺産分割の見直しを求めることが可能です。
- 遺産分割のやり直しを行う方法
(1) 相続人全員の合意がある場合
- 相続人全員で話し合い、新しい分割方法を決定する。
- 新たな遺産分割協議書を作成する。
- 必要に応じて、名義変更・登記手続きを行う。
(2) 合意が得られない場合
- 家庭裁判所に調停を申し立てる
- 相続人間で意見がまとまらない場合、家庭裁判所の「遺産分割調停」を利用することができます。
- 訴訟(審判)を申し立てる
- 調停でも解決しない場合は、裁判所が遺産分割の内容を決定します。
(3) 遺産分割協議の無効・取消しを主張する場合
- 無効や取消しの理由を証明する証拠を集める。
- 必要に応じて、家庭裁判所に訴えを提起する。
- 遺産分割のやり直しに関する注意点
- すでに財産を第三者に譲渡している場合
- 遺産分割後に不動産や株式などを第三者に売却してしまった場合、やり直しは困難になります。
- 税務上の影響
- 遺産分割のやり直しを行うと、贈与税が発生する可能性があるため、税務上のリスクも考慮する必要があります。
- 時効に注意
- 遺産分割の無効や取消しを主張するには**一定の期限(民法の規定による時効)**があるため、早めに対応することが重要です。