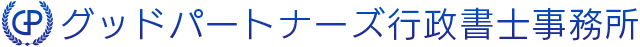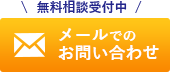コラム
column
戸籍のたどり方について
戸籍のたどり方について
戸籍をたどる方法とは戸籍という制度があります。簡単に言えば「国民一人一人を出生や婚姻関係などによって家族単位で登録する制度」のことで、私たちの法的な身分関係を示すものとして、パスポート発行や相続手続きなどに利用されています。
この戸籍は、婚姻や分籍(現在の戸籍から抜けて単独の戸籍を作ること)などがあれば新戸籍が作成されます。ですから一人の人間の戸籍は一つだけでなく、いくつにもまたがって連続していることが多いのです。これが戸籍制度を複雑にしている理由とも言えます。
そしてそれらは同じ本籍地にあるとは限らず、必要な場合はそれぞれの戸籍の本籍地である市区町村に請求することになります。相続手続きにおいてはしばしばこの問題が起こります。例えば、父の相続でどのような戸籍が必要か。父が生まれてから亡くなるまでのすべての居住地で、それらを集める必要があります。
しかし父は転勤が多く、あちこちに住所を変えていました。すべて郵送でも可能ではあったのですが日数がかかってしまうため、結局は自分で足を運ぶこともあります。

このように戸籍をたどることができるのは、戸籍には必ず入籍日とその一つ前の従前戸籍が記載されているからで、必要な場合はまず死亡時の本籍地で請求し、そこから順にさかのぼって取得して行きます。
また戸籍には「附票」というものがあります。これは本籍地の市区町村において原本と一緒に保管されている書類で、その戸籍が作られてから現在に至るまでの住所が記録されています。それを住民基本台帳と照らして閲覧すれば、転居の履歴が判明します。それによって連続した戸籍をたどることができるというしくみです。
相続手続きにおいて被相続人の戸籍をたどるのは、その配偶者や子供の有無などを確認し、誰が相続人なのかを確定させるためのものです。配偶者や子供がいない場合は、父母や兄弟姉妹の戸籍を調べる必要があることもあります。
また被相続人が亡くなった時に凍結された銀行口座を解除する手続きにおいても、必要書類の一つとしてその出生から死亡までの戸籍謄本を求められます。
これらの作業は思った以上に大変ですが、誰かがそれを行わなければなりません。