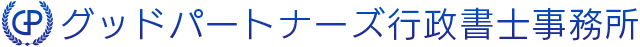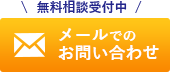コラム
column
認知症に備えるために
テレビでも最近よく聞く認知症
認知症に備えるために
わが国は今、人口が減少する一方で高齢化が急速に進んでいます。総務省の発表では2022年10月時点で65歳以上の高齢化率は29%に達しており、2050年には37%になると予測されています。それと並行して認知症の人が増え、2年後の2025年には約700万人と65歳以上の5人に1人が認知症になると見込まれています。
確かに最近は、そうした方が決して珍しくはないことを実感するようになりました。こうした認知症になると、当然ながらさまざまな困った問題が発生します。記憶が曖昧になり物事が覚えられなくなったり、簡単な計算や判断ができなくなったりします。
その結果いろいろなトラブルや詐欺などに巻き込まれやすくなります。生活資金の面でも、預貯金口座の解約や引き出しができなかったり、不動産や証券の売買、保険の解約や受取り請求ができなくなります。また介護費用を家族が負担する場合は、生活が圧迫されることになります。
さらに相続においても遺言書の効力をめぐって争いが起こるケースやさまざまな相続手続きができなくなります。これは被相続人だけでなく相続人が認知症となった場合も、遺産分割協議ができなくなるなど同じ問題が起こります。

ところで法律的な行為(契約)において、認知症はどのように判断されることになるのでしょうか。一般的に契約は双方の意思の合致によって成立しますが、それを有効に締結するには「意思能力」と「行為能力」の2つが必要とされます。「意思能力」はその行為の結果を判断できる能力で、これを欠く人の契約は無効とされます。認知症の人は、民法上「意思能力」のない者として扱われます。
また「行為能力」は単独で有効な契約を行なうために必要な能力で、その能力に欠けた人の契約は取り消すことができます。この「行為能力」が制限された人は「制限行為能力者」とされ、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人などがこれにあたります。
その能力を補う者として成年後見人や保佐人、補助人等が定められています。すでに認知症となった場合は、こうした人にサポートしてもらうことになります。
一方で認知症になる前であれば、「任意後見制度」や「家族信託」の活用といった方法があります。「任意後見制度」とは将来自分の判断能力が不十分になった時に備えて、後見人を依頼し、その内容を契約(公正証書)で決めておく制度です。
また「家族信託」も認知症になった場合に備え、ご自身の財産の管理を親族など信頼できる人に任せておく制度です。
元気なうちに将来のことを家族などで話し合い、必要な手続きをしておくことをぜひお勧めいたします。