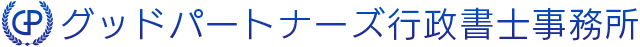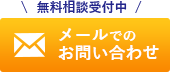コラム
column
家族葬
「家族葬」とお墓の形の変化
少子高齢化とともに、わが国の葬儀の形も近年大きく変化しつつあります。ある研究所が昨年50~79歳の男女2,000人を対象に行った『終活に関する意識調査』によると、自分の葬式は「家族葬」でと答えた男性は50.3%、女性が50.1%、また「一般葬」は男性7.6%、女性3.5%で男性が多く、逆に「一日葬」「直葬」は男性より女性の方が多くなっています。さらに「お葬式はしない」(まだ決めていない人も含む)が全体で24.9%との結果でした。
このように家族葬が急速に増えつつあり、男女ともにほぼ半数となっています。
「家族葬」とは家族や故人と親しかった方の少人数で行うものを指しますが、明確な定義があるわけではありません。式自体は一般葬とほぼ同じで、お通夜と翌日の葬儀・告別式という流れになります。
ただし少人数で行うため、家族や参列者の思いをより反映させやすいという特徴があります。その形式をどのようにするか、また故人と関係のあった方のどの範囲までお招きするかなども自由に決めることができます。費用も比較的安価に抑えることができるため、時代の流れに沿った葬儀と言えるようです。

このような葬儀の変化とともにお墓の形も、大きく変わってきています。かってはお墓と言えばいわゆる和型のお墓を指し、お盆になれば故郷に帰ってお墓参りをするのが一般的でした。しかし葬儀と同じくお墓も多様化し、日本古来の風習もしだいに変化しつつあります。
最近の別の調査によれば購入したお墓の種類では「樹木葬」が48.2%で、約半数を占めました。これは何も残さず自然に帰りたいという断捨離の感覚と共通するようで、お墓も承継者不要のものを希望する人が増えてきています。
またお墓に納めた遺骨を他のお墓や納骨堂に移す「改葬」や(厚生労働省の調査では2022年度全国で15万件以上)、墓石を撤去する「墓じまい」も増えています。特に高齢者は自分たちが苦労してきた分、子や孫にはお墓のことで苦労させたくないと考えているようです。近年、地震や水害でお墓が流されたり壊れたりしていることも影響しているようです。
その他に「海洋葬」「山葬」(散骨)といった選択肢も広がっています。さらにお墓の形も従来の和型ではなく、1平方㍍以下の小型墓が増えています。それとともに仏壇も小型化していて、小さなスタイリッシュな仏壇や、遺骨や遺灰の一部をペンダントやアクセサリーに納める「手元供養」、またガラス製位牌などの新しい形も登場してきています。時代と共に変化してきていますね。