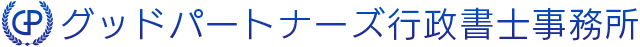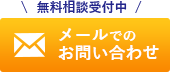コラム
column
離婚について
「熟年」離婚と「円満」離婚
厚生労働省の発表によると2023年のわが国の離婚件数は速報値で約18万7800組で、2022年よりも4700組(2.6%)増え、5年前の2019年以来の増加に転じました。
離婚件数は2002年の約29万組をピークに減少傾向が続き、過去5年をみると新型コロナの感染が拡大した2020年は約19万3200組で前年より1万5200組減少、その後も減り続けていましたが昨年増加に転じました。
その背景には夫婦のあり方についての価値観変化や女性の経済的自立があるとされます。婚姻件数に対する離婚件数の割合は、ここ10年ほど見るとおよそ35%に達しています。

2022年に離婚した夫婦のうち、同居期間20年以上の「熟年離婚」は約3万9000組(23.5%)で、前年から0.8ポイント上昇。統計のある1947年以降で最高となり、4万組前後で高止まりしています。高齢化により夫婦の老後が長くなったことで、人生を再設計するケースが増えたことが背景にあるようです。同居期間の内訳は、20年~25年未満が約1万6400組、25年~30年未満が約1万800組、30年~35年未満が約5200組、35年以上が約6600組となっています。
熟年離婚の比率が高まっている理由としては、以前に比べ男性の平均寿命が81歳まで延び、夫の定年後に夫婦で過ごす時間が長くなり、性格の不一致などで新しい人生を歩もうとするケースが目立っているようです。また最近はその前段階で夫が管理職から外される「役職定年」で収入が減少し、夫婦間に亀裂が生じて離婚に至るケースも多いとされます。
この離婚ですが、実は3月の届け出が最も多くなっています。昨年の場合、他の月は1万5千組程度なのに対し3月は2万組を超えています。過去のデータでもこの傾向は続いています。やはり3月は子供の進学や就職、さらには経済力をつけるための転職など、新年度に向けて区切りをつける人が多いためと思われます。
結婚式の「新郎・新婦」に対し、離婚式では「旧郎・旧婦」。離婚をネガティブに考えるのではなく、離婚に至った理由と向き合うことで、新たな自分たちの成長の機会とすることを目的とします。他人には言いにくい離婚原因を親戚や友人にオープンにすることで、離婚後も良い関係を保ち、引き続き協力して子どもを育てることなどを参列者の前で誓うそうです。
費用は10万円から20万円ほどで「未練を断ち切りたい」男性から提案することが多いようですが、結婚も離婚も自分たちの未来のためですから、ぜひ前向きにとらえて次の新しいステージに進んでもらいたいものです。