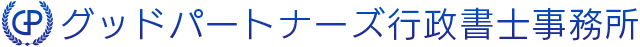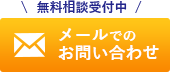コラム
column
国籍と夫婦別姓問題について
国籍と夫婦別姓問題について
アメリカのトランプ大統領が就任早々、国籍の「出生地主義」を廃止する大統領令に署名しましたが、連邦地裁が一時的差し止めを命じたとのニュースが流れました。国籍は国家という共同体の構成員であることを示す資格のようなもので、相続においても重要な問題となります。
「出生地主義」とは誰でもそこで生まれただけでその国の国籍が得られるもので、これに対するものとしては親との血縁によって定める「血統主義」があります。ただしどちらかだけで決めるのではなく、もう一方も補完的に考慮して決めるのが一般的と言われます。

トランプ大統領は不法移民対策の一環として実施しようとしていますが、ちなみに「出生地主義」が多いのは北中南米の国々で、アメリカの他、カナダ、ブラジル、アルゼンチンなどです。アジアでは、今回のアメリカと同じようにバングラデシュからの不法移民に悩まされたインドは2004年にこれを変更しています。
日本は原則として「血統主義」で、フランスやドイツといったヨーロッパの先進国も以前は「出生地主義」を採用していましたが、いずれも二十世紀に入ってから「血統主義」に変更しています。
この「血統主義」は、国家というのは血縁や民族としてのつながりが基本であるとの考え方から生まれたもので、親子関係が重視されています。そしてこの「血統主義」には父母の国籍が関係しています。
父母の国籍が同じであれば問題はないのですが、両方の国籍が異なる場合に、父の国籍が自国であればその子にも認められるのを「父系優先血統主義」と言います。また父母どちらかの国籍が自国であれば、その子にも認められるのを「父母両系血統主義」と言います。
ですから「父系優先血統主義」の国においては、母の国籍だけ自国の場合にはその子が認められるかどうかはそう簡単ではありません。
これを聞くと、最近日本で大きな問題になっている「選択的夫婦別姓」を思い出します。それは単に夫婦の姓をどうするかという「旧姓の通称使用拡大」などに止まらず、その子供の姓をどうするかが問題の根本となっています。すなわち父母(夫婦)とその子供の関係をどうするかという問題です。その意味では、国籍の話とよく似た側面を持っています。
これについては血縁や共同体という国家の伝統をどう守るかというナショナリズムの問題が根底にあるだけに、なかなかすっきりと解決するのは難しいと言えます。すでに30年近く検討されているわけですが、はたして近いうちに明確な方向を打ち出せるのでしょうか。それともまた先送りとなるのか、注目されるところです。