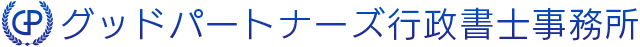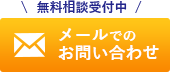コラム
column
相続税が2割加算される相続人とは
相続税が2割加算される相続人
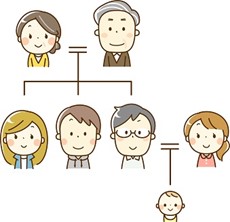
相続人の一般的な範囲は、遺贈などによる特別な人を除いては配偶者と子供や孫、父母、祖父母、兄弟姉妹などの親族です。この中で配偶者は常に相続人となり、それぞれの相続順位は子供が第一順位、父母や祖父母が第二順位、兄弟姉妹が第三順位となります。たいていの場合は、これらの人が相続することが多いと思われます。相続人が確定すれば次に遺産分割協議などにより相続金額を調整し、それぞれの相続税を計算して行くことになります。
その際に、これら相続人と被相続人の親等の違いにより、相続税額に差が設けられることがあります。各自が受け取る相続財産の額の違いで税率に差があるのはわかるとしても、親等の違いで税額が変わるのはなぜという疑問を抱かれるかもしれません。その根拠になっているのは相続税法第18条です。少し長いですが引用します。
「相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人となった当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。」
つまり配偶者や一親等の子供または父母以外が財産を相続すると、相続税額は2割加算されることになります。このような規定はなぜ生まれたのでしょう。その理由としてよく言われるのは、相続の税負担を調整して公平性を保つためということです。
具体的には例えば子供がいてもいずれは死んで孫に遺産が相続されるのなら、子供を飛ばして直接孫に相続するといったケースが考えられます。本来なら子供が相続していったん相続税を支払い、さらに子供が死んで孫に相続する時にもう一度相続税を支払うのが一般的ですが、税を支払う機会が一度だけになり税負担が少なくなってしまいます。そのため税負担を調整しようという考え方により、こうしたケースでは相続税額に2割加算することになったわけです。
たしかに孫への相続の場合は頷ける気がしますが、では祖父母や兄弟姉妹でも同じことが言えるのかと突っ込まれそうです。一親等ではないので間を飛ばしているというのはその通りかもしれませんが、それによって誰かの税負担が軽くなるかと言えばそれはあまり関係ない気もします。
これはおそらく、相続というのは本来は配偶者や子供(または例外的に父母まで)のためのものであり、祖父母や兄弟姉妹はもともと被相続人との関係もそれほど濃いものではなく(特に兄弟は他人の始まりとよく言われ遺留分もありません)、優遇される理由はないということではないでしょうか。
それはともかくとして、この相続税の2割加算についてはご存知ない方も多いように思われます。さらに言えばこれは孫や祖父母、兄弟姉妹だけに適用されるのではなく、甥や姪、さらには内縁の妻(夫)、あるいは遺贈により財産を受け取る人などにもあてはまります。ご自分ないしはご家族の将来の相続を想定して、このようなケースが考えられそうな場合はあらかじめ注意しておきたいものです。