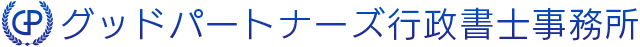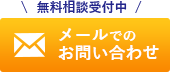コラム
column
空き家の有効活用について
空き家の有効活用を考える
空き家の問題を考えてみたいと思います。これについては相続登記の義務化と関連することがあります。少子高齢化の急速な進展とともにわが国の空き家は年々増加し、ある予測では今年は1,293万戸、空き家率は19.4%に達するとも言われています。約2割ですから5軒に1軒です。増加率は年々鈍化しているものの、やはり大変な数であることは間違いありません。空き地と同様に、景観や防犯上さらには衛生面など様々な問題を抱えていると言えます。
中でも最近目に付くのは、高齢者が亡くなられて大量の家具や物品が遺品として放置されたままの空き家です。一人暮らしや施設に入居したまま亡くなる高齢者が増えると、長年にわたり家具や物品が放りっぱなしとなり、また不用品やゴミも多くなります。そうした状態の空き家を相続した場合、その遺品や不用品の多さに困惑してしまうといったことも起こります。
こうした時にはその処分方法を考えることも大事ですが、その前にまず空き家自体をどうするかを決めるのが先決と言えます。特に相続人が複数の場合はよく話し合って、売却という選択肢なども含め、慎重に検討する必要があります。すなわち空き家を建物として残し再利用するのか、あるいは全て取り壊して更地にするのかなどです。
利用目的によっては固定資産税など税制の問題も関係しますので、十分な比較検討が望まれます。
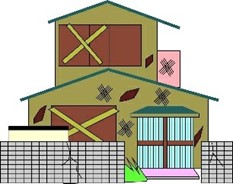
建物を残す場合は、古い家具は再利用するといったことも考えられます。レトロな雰囲気を持つ家具は、若い人にとっては大いに利用価値がありそうです。屋根や柱、壁なども築年数による老朽化の度合いを見究めて補修すれば、まだ十分使用に耐えるかもしれません。
そんな中で最近注目されているのが、相続人が所有者のまま空き家をDIY賃貸住宅とする方法です。これは不動産業者が仲介して行なうもので、空き家をDIY賃貸住宅として貸出し、入居者が自分のライフスタイルに合わせてDIYリフォームを行ないます。屋根や柱などは保持したまま取り壊す必要がなく、所有者にとっても賃借人にとってもメリットのある方法と言えます。
このようにあらかじめ建物をどうするか決めた上で、家具や物品をよく確認し、その処理方法を検討するのが良いと思われます。そのまま再利用するのか、他の相続人が引き取るのか、あるいは誰かに売却するのか捨てるのかなどを決めて行きます。業者に処理を依頼する場合は、家具や物品数が多いとかなりの費用が発生することもありますので注意が必要です。
いずれにしても建物や家具などの再利用が一つの大きな流れとして定着し、多くの空き家が有効に活用されることを願うしだいです。