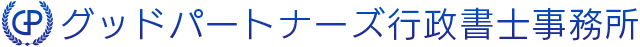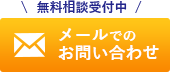コラム
column
半血兄弟とは
半血って、何のこと?
このコラムでも時々取り上げていますが、相続には民法関係の用語が多く、耳慣れないものもあります。この半血(はんけつ)もそうです。辞書やネットで「はんけつ」と入力しても、判決や半尻(お尻の上半分が見えている)が出てくるだけです。
ネットでは漢字で入力するとさすがに正しい言葉が出て、異母兄弟姉妹や異父兄弟姉妹など半分だけ血がつながっている関係とわかります。ですから両親とも共通の兄弟姉妹は、全血(ぜんけつ)の兄弟姉妹ということになります。
近年の統計では、年間の婚姻数は約60万件なのに対し離婚数は20万件ほどで、そのためよく3組に1組の割合で離婚すると言われます(すぐに離婚するわけではなく、婚姻から一定年数が経過しての離婚ですから、この言い方はやや誤解を招きますが)。
ここで注目したいのは婚姻数の内、夫婦いずれかまたは両方が再婚というケースが約18万件に上ることです。これらの数字を見ると、昔のように夫婦が生涯我慢して連れ添うということは少なくなり、離婚や再婚はある意味で当り前のようになったと言えます。その結果、父母いずれかが連れ子を伴って再婚しそこに新しい子が生まれると、半血の異母兄弟姉妹や異父兄弟姉妹が誕生することになります。
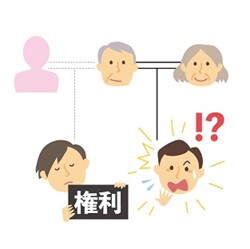
このような半血の兄弟姉妹であっても、通常その両親が亡くなった場合などは子供として同等の相続割合で相続できます。ただし特定のケースでは1/2になることがあります。
例えば被相続人に子供がなく、直系尊属もすでに亡くなっていて、相続人としては全血と半血の兄弟姉妹が2人だけいるといった場合です。全血同士なら半分ずつとなりますが、この場合は半血は全血の1/2となるため、全血が2/3、半血が1/3の相続割合となります。
この半血の兄弟姉妹と似たような言葉として、非嫡出子があります。これは婚姻していない男女の間に生まれた子供という意味です。一般的に母親と子供は自動的に親子関係となりますが、父親が子供と親子関係を結ぶには「認知」の手続が必要です。そのことにより出生時に遡って親子ということが認められます。
この非嫡出子ですが、以前は相続において嫡出子の1/2となっていましたが、平成25年の民法改正により同じ法定相続割合となりました。男女が婚姻しているいないに関わらず、子供には同等の権利を与えるという考え方によります。
いずれにしても現代においては夫婦や親子関係が多様化し、相続においてもなかなか込み入った事情を抱えるケースが増えています。
相続手続きの基本としては、まず相続人が誰なのかを確定させることが前提となります。ふだんから付き合いのある親族だけならともかく、遠方に住んでいて関係がよくわからなかったり、あるいは被相続人の戸籍を調べたところまったく知らない人が子供として認知されていたなどということもあります。
遺産分割協議を行うには相続人すべての参加が必要ですが、こうした場合は話がまとまりにくいことが多いので、事前のきちんとした準備や対策が欠かせないと言えます。