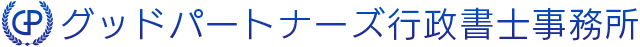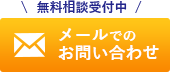コラム
column
死因贈与
「死因贈与」ってどんな意味?
先月は相続の「代襲」ということを取り上げましたが、今月も引き続き相続関係の耳慣れない言葉についてふれてみたいと思います。その一つが「死因贈与」という言葉です。
普通「死因」と聞けば何が原因で死んだのか、という意味だと思いますよね。するとそれと「贈与」とが結び付かず、えっ?となってしまいます。どうやら意味が異なる使い方をしているようです。ここでの「死因」は死亡原因ではなく、死亡の結果として発生することがらを指します。つまり死亡によって初めて効力が発生する「贈与」、という意味になります。そう言われるとそんな気もしますが、何だかわかりにくい日本語ですね。
そしてここでまた、ある疑問が起こります。それはよく似た言葉として「遺贈」というのがあり、それとどう違うのかということです。一般的に相続は死後に発生するものであるのに対し、贈与は生前に行われるものです。さらに相続は基本的に法定相続人を対象とするのに対し、贈与は相手を自由に選べると述べました。これはその通りなのですが、話が少しややこしくなるのは遺言による贈与すなわち「遺贈」という言葉もあることです。

「死因贈与」に戻すと、遺言による贈与である「遺贈」とどんな違いがあるのでしょうか。その違いとしてあげられるのは、まず「遺贈」はその内容を受け取る人に事前に知らせる必要はありませんが、「死因贈与」は通常の贈与と同じように書面に内容を記入して両者が契約します。場合によっては口頭で約束して成立させることも可能ですが、一般的には契約として書面で残す方が望ましいと言えます。このことは逆に言えば、「遺贈」はあくまでも遺言者の意思を示しているだけでそれが死後に確実に実行されるという保証はありませんが、「死因贈与」は契約によってお互いにその実行を担保していることになります。
さらに「負担付死因贈与」と言いまして、相手に対して何らかの負担(義務)をしてもらうことを条件に死後贈与するという方法もあります。例えば生前に、自分の身の回りの世話や介護をしてもらうといったことです。なお「死因贈与」は「遺贈」と同じように後で撤回することは可能ですが、この「負担付死因贈与」の場合は特段の事情がない限り撤回できないとの判例もありますので注意が必要です。
また「死因贈与」の一つのデメリットとして、相続人が不動産を相続する場合は登録免許税として固定資産税評価額の4/1000で済みますが、「死因贈与」により受け取る場合は20/1000と5倍になります。また前者では不動産取得税がかかりませんが、後者では一律4%ほどが課税されます。このようなことも考慮しながら、それぞれの事情に合わせて最善の方法を選ぶのが望ましいと言えます。