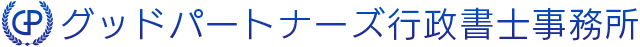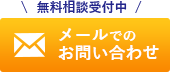コラム
column
名義預金と定期贈与について
「名義預金」と「定期贈与」
今回は「名義預金」と「定期贈与」の話をしてみたいと思います。この二つは贈与に関係する言葉ですが、実はどちらも税務上は大いに問題があることとされます。そこでまず贈与について、簡単におさらいをしておきます。
贈与とは自分の財産を無償で誰かに与える意思を表示し、相手がそれを受託することで成り立つものです。その約束は口頭でも書面でも良いのですが、お互いの意思を明確にするため贈与契約書を作成しておくのが望ましいとされます。
この贈与には生前贈与と死後の贈与の二つがあり、一般的には生前贈与を指しますが、死後に行われることもあります。死後の贈与は、さらに「死因贈与」と「遺贈(いぞう)」の二つに分かれます。その違いについてはこのプログで取り上げたこともあります(2021年2月)。簡単に言うと「死因贈与」は死亡により財産を指定した人に贈与する契約をあらかじめ結んで実行するのに対し、「遺贈」は遺言によって指定した人に財産を贈与するものですが相手との契約(合意)はありません。このように「遺贈」を除いては、贈与にはお互いの意思表示のための契約(合意)が必要となります。
話を「名義預金」に戻しますと、これは口座の名義人と実際にお金を出した人が異なる預金を指します。例えば祖父母がお孫さんのためにその名前で勝手に預金通帳を作ってお金を積み立て、いつのまにか一千万円を超えたなどです。
しかし相続が発生した場合には、これは生前贈与によるお孫さんの財産とは見なされず、祖父母の相続財産として扱われ課税対象となることが多いのです。名義はお孫さんの名前ですが、実質は祖父母の財産と判断されてしまいます。
これを避けるためには、生前贈与としての客観的な証拠を残すことが求められます。

もう一つの「定期贈与」というのも、あまり耳慣れない言葉です。年間110万円までは贈与の課税対象にならないことはよく知られていますが、それはあくまでも個別的な贈与の場合です。
例えば1,100万円の財産を毎年110万円ずつ分けて10年間定期的に贈与を実行した場合は、まとめて1,100万円の贈与をしたと見なされる恐れがあります。これが「定期贈与」と呼ばれるもので、毎年の個別的な贈与とは異なると判断されることがあります。こうした場合は、毎年贈与の時期や金額を変える方が望ましいと言えるようです。
何だかすっきりしないと思われるかもしれませんが、税務においてはよくある話ですので注意が必要です。