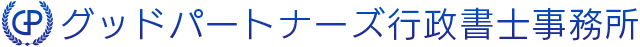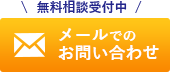コラム
column
みなし相続財産としての生命保険
みなし相続財産としての生命保険
今回は、生命保険についての話です。
生命保険と言えばミステリーなどでよく保険金目当ての殺人事件に利用されますが、相続においては生命保険はみなし相続財産として位置付けられます。
それは生命保険というものがあらかじめ被相続人の固定した財産として存在するのではなく、当人が亡くなって初めて保険金として受取人(相続人)に支払われるためそう呼ばれています。
生命保険はもともと相互扶助を目的に、家計の担い手が亡くなった時に残された家族が安心して生活できるよう考えられたものです。ですから普通の預貯金などと違い、相続時には税制面で非課税枠の優遇措置があります。
これは死亡退職金にも同じように適用されますが、具体的には次の通りです。
◆500万円×法定相続人の数
例えば法定相続人が配偶者と子供二人の計三人の場合は、1500万円が非課税枠となり、それを超える部分が相続財産として課税対象となります。ですから預貯金などで所有しているよりも、税制面では有利となります。また生命保険ではそれまで払い込んだ掛け金(保険料)よりも死亡保険金が大きくなるのが通常ですから、その面でもお得ということになります。
生命保険の内容は時代とともに変化し、現在では多様な商品が開発されていますが、基本的な種類は次の三つと言われます。
①掛け捨て型の期間限定の「定期保険」
②同じく期間限定だが貯蓄型の「養老保険」
③養老保険を一生涯保障にした「終身保険」
超高齢化時代の保険としては、途中で肝腎の保障が切れてしまう①②よりは③の終身保険が確実と言えます。ただ気を付けて頂きたいのは、これらをいろいろ組み合わせた商品が多いことです。
例えば名前は終身保険のようでも、大部分が掛け捨て型の定期保険だったりすることもあります。その場合は高齢になってからの保障がきわめて小さくなったりするので、気を付けなければなりません。
また為替で変動する外貨建て保険や運用成績で変動する変額保険などもありますので、相続にきちんと役立つ内容なのかどうかあらかじめよく確認することが大切と言えます。
生命保険の契約には、契約者(保険料を払う人)、被保険者、受取人の三者の指定が必要です。一般的には家計を支える本人(親)が契約者かつ被保険者となり、配偶者や子供を受取人とする契約形態が多いと言えます。ただし被保険者が本人でも契約者が本人以外だとみなし相続財産とならない場合もありますので、契約形態には注意が必要です。
生命保険が相続対策として優れている点は、保険金額が確定しておりしかも非課税枠があること、さらに保険金が分割可能な現金であるため相続時に代償分割しやすいことがあります。このような多くの利点のある生命保険を、ぜひ有効に活用していただきたいものです。