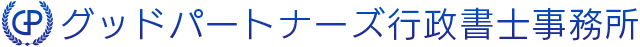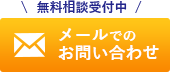コラム
column
特別寄与料について
非相続人の「特別寄与料」について
いよいよ改元の年を迎えました。今年は大きな地震や台風、豪雨災害などのない平穏な一年であることを祈りたいものです。
さて昨年は40年ぶりに相続法が改正され、今年から新しい制度が始まります。この欄でも「配偶者居住権」のことや、先月は「相続された預貯金債券の仮払い制度」などを取り上げてきました。今回はもう一つ新たに設けられた「特別寄与料」の請求制度について触れてみたいと思います。
これは簡単に言いますと、相続人以外で被相続人の生活や財産の維持などに関して特別な寄与や功労のあった人に対しては、その分を金額に換算して認めてあげようという制度です。
ですからまず確認していただきたいのは、相続人であるかどうかという点です。具体的な例としては、一般的に親が亡くなった場合に子供は相続人となりますが、その配偶者は親族ではあっても相続人ではないので、遺産を受け取る権利はありません。子供の配偶者が一生懸命に介護をしていたとしても、そもそも相続権がないので何ももらえないのです。

近年高齢者の介護は大きな社会問題となっており、こうしたケースで義父母などの介護に多大な尽力をしていても、法定相続人ではないとの理由で何の対価も認められないのはやはり不合理と言わざるをえないでしょう。
そこで今回の改正では「特別寄与料」として、子供の配偶者などがそれまでの介護に費やした労務や時間に応じて相当する金額を請求できるようになりました。請求する相手は、被相続人の遺産を引き継ぐ相続人に対してということになります。
制度の趣旨はこのようなものですが、現実的にはその請求金額をどう計算するかといった問題が残っています。詳しい計算方法などはまだ公表されていませんが、考えられるのは一般的な介護職員が受け取る時間給の額に介護に費やした時間を掛け合わせるなどの案が検討されているようです。
しかしまだ曖昧な点もありますので、少なくともこうした状況に置かれていると思われる方は、介護日誌をつけるなどして記録として残しておくことをおすすめいたします。
なおこの寄与料の金額について相続人との間で合意ができない場合は、家庭裁判所に申し立てをすることができます。こうした問題を起こさないためにも、生前にこのような立場で尽力している非相続人がおられる場合は「特別寄与料」を遺言で言及しておくことが望ましいと言えます。