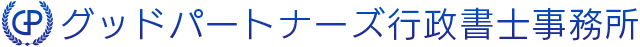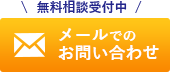コラム
column
不要な空き地をなくすには
不要な空き地をなくすには
近年、空き家や空き地の問題が大きくクローズアップされています。これには核家族化や少子高齢化、さらには相続や登記などの問題が複合的に関係しているため、その解決は容易ではないように思われます。今月はその中で、まず空き地の問題を取り上げてみたいと思います。
一口に空き地と言っても、そもそも所有者が不明というのもあれば、所有者は明確でも何らかの理由により利用されていないというのもあります。そして私たちの普通の感覚では、所有者は明確だが単に利用されていないだけというのが多いように思われますが、そうとばかりも言えないようです。以前の国交省による所有者不明土地の実態調査によれば、全国で所有者が不明の土地は20.3%もあり、面積では410万haにも及ぶとのことです。ちなみに九州の面積が368万haですから、それより広い土地が所有者不明ということになります。
これには都市部だけではなく農山村部も含まれますから、それほど驚くような話ではないのかもしれません。しかし日本の国土のうち2割余りが所有者不明というのは、土地という資源の有効活用や国土保全の観点からも決して望ましいこととは言えないでしょう。当然ながら所有者不明のままでは何をすることもできないため、国として解決のための抜本的な方策が求められるところです。

一方で、所有者は明確でも全く利用されていない土地があります。これについては「相続土地国庫帰属制度」というのが始まりました。これは簡単に言えば相続した不要な土地を、国が引き取る制度のことです。
利用されていない土地の相続が重なっていくと、相続人の関係もしだいに複雑になり、きちんとした登記や売却、相続放棄などが簡単にできなくなります。そしていつしか所有者不明となり、土地は荒れていき管理も困難になります。そうしたことを防ぐために国が引き取る制度ですから便利とも言えますが、注意すべきいくつかの条件があります。
まず申請をするには、建物がない更地であることが必要です。空き家があれば自己負担で取り壊しや滅失登記を行います。また土地の利用者がおらず、担保権などが設定されていないことや、境界線が明確であることなどの条件が設けられています。(法務省のホームページに18項目掲載されています)
申請は相続人が行い、共有地の場合は全員の合意が必要です。合意が得られなかったり、登記をしておらず所有権の確認が困難な場合は申請は認められません。
このような条件を満たしている場合でも、国に引き取ってもらうには土地一筆当たり1万4千円の審査手数料や原則20万円(面積に応じ一定額が加算される場合もある)の負担金が発生する点に注意が必要です。
このように見てくると、新たな所有者不明の土地をなくすために一定の効果はありそうですが、引き続きこの制度を利用しやすくするためにはなお一層の改善が求められると言えます。